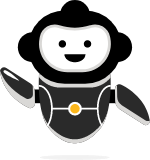-
-
October 24, 2022 at 11:46 pm
Naritoyo Shibata
Ansys Employeeマルチボディパーツ(節点共有あり)はジオメトリエディタ等での設定作業が必要となり、また多くのケースにおいて計算負荷上の差異がさほどないことから、一般的にはアセンブリパーツ(節点共有なし・ボンド接触で接合)を推奨いたしますが、一例として以下のような違いから判断して選択していただくこととなります。
マルチボディパーツ(節点共有あり):
・接触設定が不要でその分計算負荷が小さくて済む。ただし、設定作業はMechanical以外のツールであらかじめ行なっておく必要があるため、作業工数がかかる場合がある。
・ボディどうしの境界部は、構造解析であれば剛な接続、伝熱解析なら熱抵抗なし、電気解析なら電気抵抗なしとなる。
・ボディ間の反力算出にひと手間必要。(APDLコマンド、もしくは作業ジオメトリのサーフェスで反力プローブ機能、など)
・節点共有のため、接合部でメッシュが必ず整合する。アセンブリパーツ(節点共有なし):
・接触設定(ボンド)が必要となり、計算負荷が大きい場合もある。
・ボディどうしの境界部について、構造解析であれば接触剛性を調整することで剛でない接続も表現できる。また、伝熱解析なら接触熱伝導率、電気解析なら接触電気伝導係数などを設定できる。
・ボディ間の反力算出が容易。(接触の反力プローブ機能)
・一般的には接合部でメッシュが整合しないので、重要度が低いボディ側のメッシュ数を節約することも可能。以上、ご参考になれば幸いです。
-
July 26, 2023 at 2:38 am
Victor Patrick
Subscriberありがとうございます、この情報はマルチボディパーツとアセンブリパーツの違いについて詳細な説明を提供していますね。
マルチボディパーツ(節点共有あり)の利点:
接触設定が不要で計算負荷が小さい。
しかし、事前に設定作業が必要で、作業工数がかかることがある。
ボディ間の境界部は剛な接続、伝熱解析なら熱抵抗なし、電気解析なら電気抵抗なしとなる。
ボディ間の反力算出に一手間必要であるが、節点共有のため、接合部でメッシュが必ず整合する。
アセンブリパーツ(節点共有なし)の利点:接触設定(ボンド)が必要で計算負荷が大きい場合もある。
ボディ間の境界部について、構造解析なら接触剛性を調整し、伝熱解析なら接触熱伝導率、電気解析なら接触電気伝導係数を設定できる。
ボディ間の反力算出が容易である。(接触の反力プローブ機能)
一般的に接合部でメッシュが整合しないので、重要度が低いボディ側のメッシュ数を節約することも可能。
これらの情報をもとに、特定のシミュレーションや解析の目的に応じてマルチボディパーツかアセンブリパーツかを選択することが重要です。ありがとうございました!-
July 27, 2023 at 7:17 am
Naritoyo Shibata
Ansys Employeeコメントいただきありがとうございました。情報がお役に立ちましたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
-
-
- トピック ‘マルチボディパーツ(節点共有あり)とアセンブリパーツ(節点共有なし・ボンド接触)はどのように使い分けますか?’ 新しい返信は受け付けていません.


-
3492
-
1057
-
1051
-
965
-
942

© 2025 Copyright ANSYS, Inc. All rights reserved.